⑥高齢者の相談 高齢者の住宅相談の特徴
高齢者の相談は
★高齢なっても住み続けられる住宅改善
『食事・洗面・入浴・排泄・更衣・脱衣・起床等の日常生活の基本的な作業を中心に検討する。』
★住宅改修を拒む高齢者
要介護者自身や高齢者自身は直接自分の為には、経済的な負担が掛る住宅の改修等の相談をしない。逆に経済的負担や家族ヘの気遣いで住宅改修自体を拒む傾向にあります。
しかし、実際には改修工事は日常生活『ADL』をなす上では利便性を高め要介護者の自立を促し介助者の介護軽減にも大きな効果がある。
経済的な負担を超越した価値を要介護者にわからしめて、その機能を充分に利用することがとても大切である。
逆にまだ充分に動ける、無理をすれば一人でも動けるのでと放置しておくと、わずか30cmのベッドから落ちて、大腿骨を骨折しそれがもとで寝たきりになり、後々まで家族全員に大きな負担強いる悪い例が大変多いことも事実です。
わずかな本人との合意での費用負担で、自立した高齢者の生活が営まれます。
高齢者とその家族にとって、住宅改修のプラスとマイナスを考えることが今とても大切な事です。
また、ほとんど障害を持つ高齢者の場合は、進行性の機能障害や運動障害だと考えて良く、仮にそうでなくても高齢者は年々加齢と自然条件のもとでは、進行性の障害に似たかたちが必ず現れてくます。
だからと言って、今日、あってすぐに専門業者、内装業者を紹介するようなところに相談に云ってもだめなのです、何度も現状と障害の事を話し合い、これから先のことを推測し、将来を見越した住宅改修のプランを建ててくれるところで相談しましょう。
高齢者の疾患や進行性の障害を理解していない内装業者と話をしても無駄、その業者のいくら腕が良くてもだめなのです。
物の理解自体が出来ていないのでいくら立派なものが出来ても、将来すぐに使えなくなってしまいます。
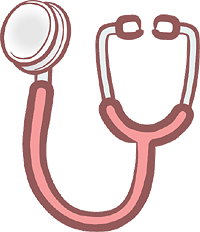  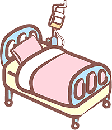
見出し※高齢者住宅改修の現場
①高齢になっても傷害を得ても、
住み慣れた自宅でできる限り長く自立して暮らすための生活基盤
の整備。(在宅生活支援の一部)
②高齢者と住環境
改修の要望がでた箇所だけでなく、本人の身体状況、家族状況、
住まい全般の状況を見る。
③在宅での生活を支える
④介護者の負担を軽くする
|
 |
見出し有効・適切な改修の為に
目的、対象、時期の把握を検討する。
1.本人の身体状況
2.本人の日常生活
3.家族(介護者)の状況
4.既存家屋の状況
5.家族を含めた将来予測
6.経済状況
その他注意すべきこと
1.建築でのすべての解決は無理
2.連帯の大切さ(保健医療福祉等)
3.自立を支える要素 本人の自立能力
|
 |

(家族・住宅・人間関係)
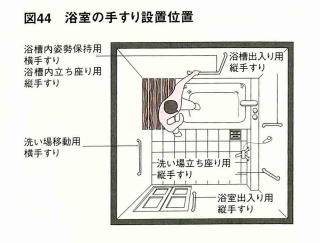
※住宅改修の基本技術
改修前の基本的チェック事項
(1) 身体状況の把握
①高齢による身体機能の把握
寒さに弱くなる。
感覚が鈍くなる。
運動機能が落ちる。
多くの女性は骨粗そう症もあって膝関節症や腰痛を
訴えることが多い。
②疾病等による傷害
脳血管障害 後遺症に麻痺が残る場合が多い。
股関節傷害 膝関節症・腰痛・転倒による大腿骨頭骨骨折。
慢性関節リュウマチ 多発性関節炎 手足の変形。
パーキンソン症候群 |
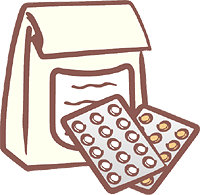 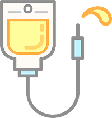 |
★参考文献 「グラフは高齢化社会 内閣府平成24年度版より」月刊総合ケア・福祉住環境コーディター検定・日本医師会雑誌「リハビリテーションマニアル」メディカルレビュー社「GERONTOLOGY」高齢白書平成24年度版 東京都住宅局福祉課資料他
 
最初はご相談から、始まります。
株式会社日本ザイカン宛
TEL
03-5368-2611へ
FAX 03-5368-2612 ご相談はメールでも 
|